まずは短めのものから
300語程度からスタート
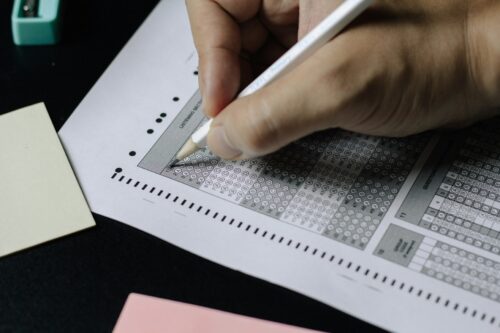
一口に長文読解と言っても100語、200語程度のものから1,000語を超える超長文まで様々です。英文解釈で精読の練習を積むので、読解の練習としてはある程度の長さ、具体的には300語程度から始めてみましょう。高校生であればCutting Edgeなど学校用教材を使っての演習の授業もあると思うので、その教材を利用するのもよいと思います。学校用教材は解答・解説があまりないのが弱みですが。完全に独学でやる場合には以下の問題集がおススメです。
- やっておきたい英語長文300-改訂版 河合出版https://amzn.to/4cinaKH
- 英語長文レベル別問題集2 初級編 東進ブックスhttps://amzn.to/3x1NCJD
- 大学入試 全レベル問題集 基礎レベル 旺文社https://amzn.to/4e9X5z0
- システム英語長文頻出問題1Basic 駿台文庫https://amzn.to/4aWJcBw

センター試験の過去問も良問揃い
共通テストに移行する前のセンター試験の英語は良問が多いです。大問5, 6以外は短いのでやりやすいと思います。語彙・構文のレベルも基礎的なので学習を始める際の教材としてはもってこいです。
夏までは時間は気にせずに
最初から時間を気にすると中途半端になってしまう
もちろん入試本番では厳しい制限時間との戦いになるので時間もゆくゆくは気にしないといけません。ただ、勉強を始めた段階で時間を気にしてしまうと中途半端になってしまいます。どういうことかというと、時間が足りないから読めなかったのか、そもそも読解力・語彙力が足りていないから読めなかったのかが分からなくなってしまいます。
ダラダラ読んでいいわけではない 時間は計っておく
とはいえダラダラ読んでいいわけではありません。必ず時間は計って解きましょう。そしてかかった時間は記録しておきましょう。多くの問題に解答目標時間が設定されています。その時間と比べてどのくらい多くかかったのか、どうすれば時短できるのかを考えましょう。
答え合わせをする前に解き直し

解いたらもちろん答え合わせをするわけですが、答えを見る前に辞書などで分からなかった単語・熟語を調べたうえでもう一度解いてみましょう。
長文読解は復習がカギ ー 語彙・構文・解答の根拠
復習ポイント①:語彙

復習するポイントは大きく分けて3つ、語彙・構文・解答の根拠です。語彙については最初に解いている段階で分からなかった単語・熟語はチェックしておきましょう。チェックした中で知っておくべき単語・熟語はノートにまとめておくとよいでしょう。「知っておくべき」の判断基準としては、単語帳に載っているかどうかで考えていいと思います。中には単語帳には出ていないけどよく見る単語というのが出てくると思います。そういうものもノートに書いておきましょう。
復習ポイント②:構文
次のポイントは構文です。読んでいて文構造が理解できなかった文は復習の段階で文構造を確認しておきましょう。時間があるときは使っている英文解釈の参考書・問題集で類題を探しておきましょう。
復習ポイント③:解答の根拠
長文読解にも様々な問題形式がありますが、最も多いのが内容一致です。「以下の文の中で本文の内容と合致しているものを3つ選べ」のようなものです。当然本文中に該当箇所があるので復習するときに確認しておきましょう。おそらくは紛らわしいけど正解にはならない選択肢があるので、どこがダメなのかを確認しておきましょう。何題も解いているとパターンがあることに気づくと思います。
毎日音読をしよう
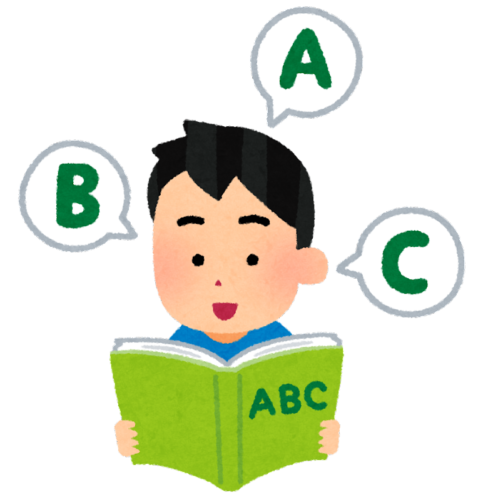
長文は毎日1題解くのが理想です。とはいえ英語だけをやっていればいいわけではないですし、長文を解く時間がない日もあると思います。そういうときは音読をしましょう。もちろんなんでも読めばいいというわけではありません。単語や文構造をしっかり理解している文を読みましょう。つまり今までに解いた長文を読みましょう。単語・熟語・構文・解答の根拠を確認しながら音読をしてください。
夏以降は志望校に合わせた学習を
ゴールを意識した学習を
長文に限った話ではありませんが、大学によって出題傾向は異なります。長文の語数もそうですし、和訳・作文・内容説明などの記述問題の有無もあります。単語を訊いてくる大学・学部もあれば、内容一致しか出ないところもあります。また、文系・理系によって出題されやすい文章のテーマも異なります。夏までに上で紹介した問題集の「標準レベル」ぐらいまでを終わらせておいて、それ以降は難易度の高い問題集に取り組みながら志望校別の対策をしていきましょう。

過去問が一番
問題集をやることも必要ですが、志望校別の対策となると最適なのは過去問です。ただ第一志望の過去問などは直前までやらずにとっておきたいというのも分かりますし、必要です。なので似たような形式の問題を解いてみましょう。例えば立教大学や学習院大学は学部は違っても出題形式は非常に似ています。なので自分が受けない学部の問題を解いてみるのもよいと思いますし、最近は入試の方式が細分化されていて同じ大学・学部でも複数回受験できる場合もあります。自分が受けない日程・方式の問題を解くのも一つの手です。また国立大学であれば一部の大学を除けば問題は似ています。自分が受けない大学の問題を解いてみましょう。
大学別の問題集を解くのも有効

全ての大学に対応しているわけではないですが「○○大学の英語」のようなシリーズを使うのもよいと思います。
東京大学への英語 駿台文庫https://amzn.to/45lJb8R
なども良書です。

すごく苦手な形式がある場合は特化した問題集も
個人的には形式別の問題集までやる必要はないと考えています。ただ「志望校にどうしても入りたいのにこの形式苦手」というような場合には形式別の問題集もやってみてもいいと思います。ただ形式が苦手なだけなのか他に原因がないかは検討しましょう。
要約・内容説明は練習が必要
上で言ったことと矛盾しますが、要約・内容説明は練習が必要です。過去問をやってもなかなかうまくいかないという場合には以下がおススメです。
- 英語 要旨大意問題演習 駿台文庫https://amzn.to/4aZoCR9
- 英語総合問題演習 駿台文庫https://amzn.to/3VmoMvQ
まとめ
長文の学習もコツコツと
言うまでもないことですが一朝一夕には読解力はつきません。語彙・構文の学習と同時に進め、極力毎日やることが重要です。新しい問題を解く余裕がない日は音読をして長文には毎日必ず触れましょう。そして短めの文から徐々に長いものにも慣れていき、夏以降は志望校を意識した学習をしましょう。復習を大切に頑張りましょう!
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39c240b0.56fa7547.39c240b1.27a7d6ab/?me_id=1237156&item_id=10002962&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgodiva%2Fcabinet%2F10319760%2F205414_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c2dc876.8269f5d0.3c2dc877.5d6ec778/?me_id=1213310&item_id=15566187&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5278%2F9784890855278_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)




コメント